『がんばれ』よりも『だいじょうぶ』
日本には、病気で入院中などの療養中でも教育を受けられる病弱教育という制度があります。病弱教育は病院内にある院内学級や隣接する病弱特別支援学校、そしてそれらがない病院に先生が訪れる訪問教育などです。その病弱教育の場で、感じたことを紹介します。
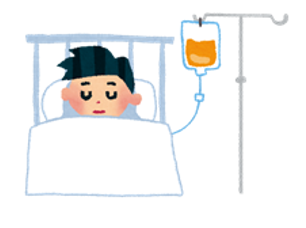
病気で入院している子どもたちは、学校の先生や友達、周りの人からよく『がんばれ』と声をかけられることが多いです。病気の子どもたちを応援する気持ちからの言葉だと思います。でもその言葉を受け取る子どもはどのように感じているのでしょうか?
白血病で大学病院に入院したある女子中学生は、突然の入院で訳が分からない中で、いろいろな人が話をしてくれても理解できなくて、わかったふりをしてとても疲れたと言っていました。『がんばろうね』って言われても何をがんばればよいのかわからなかったそうです。そんな時に唯一理解できたのは、主治医からの『だいじょうぶ』という言葉でした。その言葉で安心したそうです。このブログの「『がんばれ』よりも『だいじょうぶ』」は、彼女が好きなポケモンの「きみのそばで~ヒカリのテーマ~」の歌詞から採ったものです。
『がんばれ』の言葉は、がんばれるエネルギーがある人には励ましになるでしょうが、不安と恐怖の中でエネルギーがなくなっている人には、『がんばれ』という言葉はこころに突き刺さります。そのようなときに『だいじょうぶ』という言葉は、安心をもたらせてくれます。また言葉がなくとも、そばにいてもらえるだけで気持ちが落ち着くこともあります。そして、治療や退院などに向けて前向きに取り組もうとする気持ちが芽生え、エネルギーが満ちてくると「がんばれ」という言葉がその子の心に届くようになります。
『がんばれ』という言葉かけは、病気の子どもたちだけではなく学校現場をはじめ様々な場面で見られます。『がんばれ』と声をかけてもらえることで気持ちが高揚し、「よし、がんばろう」となる子もいます。でもがんばるエネルギーが枯渇している時は、安心をもたらす働きかけが大切です。またどのようにがんばれば良いのかわからない子には、何をどのようにすればよいのか、どのくらいすればよいのかなど具体的に示した言葉かけが必要になってきます。
同じ言葉でも、受け取る子どもによって異なったメッセージを伝えます。まずはその子を理解する想像力を働かす大切さを、病気の子どもたちを通して学ばせていただきました。
担当:江川正一
