研究室紹介
研究室一覧
障害者福祉-矢島研究室
教員紹介

矢島 雅子 やじま まさこ
担当科目
障害者と福祉、現代社会と福祉
研究分野
社会福祉学 (障害者福祉論)
研究のこだわり
障害のある当事者や家族、支援者とともに課題や解決策を考え、研究に取り組んでいます。当事者の思いは社会に届きにくい傾向にあり、一人ひとりの声に耳を傾け、代弁者になりたいと思っています。
2年間のゼミの流れ
1年目は各自が関心をもっている研究テーマについて幅広く文献を調べます。そして、研究したいテーマを決め、研究計画書を作成します。2年目は研究計画書に基づき、インタビュー調査等を行い、研究の結果と考察をまとめていきます。ゼミでは発表や意見交換をしながら、それぞれが学びを深められるようにします。
先輩の声 Sさん
障害のある子どもたちの支援を研究したい
将来は社会福祉施設でソーシャルワーカーとして働くことを希望しています。障害のある子どもの支援に関心をもち、障害者福祉ゼミを選びました。卒業研究では支援を必要とする子どもたちや保護者、支援者にインタビュー調査を行い、子どもたちのストレングスに気づきました。子どもたちが豊かな社会経験を重ねて成長していけるよう、ストレングを伸ばす支援について学ぶことができました。
研究テーマ
障害のある人の親亡き後を見据えた地域生活支援拠点の在り方
概要
近年、「8050問題」や「老障問題」の現状が報告されていますが、障害のある人が親亡き後も安心して地域で暮らすための支援はどの程度整っているのでしょうか。各自治体は地域生活支援拠点等の整備を進めていますが、生活相談や緊急時の対応、日中活動や余暇の支援に関する社会資源は不足している現状です。障害のある当事者や家族はどのような社会資源を必要としているのか、アンケートとインタビュー調査によって情報収集しています。そして、各自治体は人々の要望にどのように応えていくべきなのか、その方策を検討しています。
障害者福祉ゼミでは、ゼミ生の希望に応じて障害児・者施設の見学をしています。また、ND協働プロジェクトに参加し、障害のある人が働く事業所と協働し、製品の展示や販売にも取り組んでいます。地域で働く利用者の方や支援者の方と交流する機会があります。


これまでの主な卒業研究トピック
自閉症スペクトラム障害の人の社会スキル
障害を持つ子どもの進路決定と保護者に対する支援
障害者福祉施設における虐待の現状と対応
発達障害についての私たち学生の意識調査
小学生時の経験と学びが及ぼす福祉的意識について
食生活デザイン-藤原研究室
教員紹介

藤原 智子 ふじわら ともこ
担当科目
食品学、調理学
研究分野
食生活学・調理科学
朝食欠食やダイエットなど生活習慣の乱れが若年女性の生殖機能(月経痛や月経周期)にどのような影響を及ぼすのかを追求することを主な研究テーマとしており、いろいろな分野の研究者と協力して全国大規模アンケート調査や動物による検証実験を行っています。
研究のこだわり
どんな小さな一歩でも研究で得られた知見は社会に還元し、人類の幸福に貢献してこそ成果といえると思っています。そのために現象に誠実に向き合いたいといつも心しています。
2年間のゼミの流れ
3年生はこれまでの食生活の中で抱いた疑問や問題点について、先行研究から課題解決のヒントを得るために、論文の探し方や読み方について学びます。また具体的なテーマを設定してゼミ全体でその課題に取り組みます。たとえば民間企業のメニュー開発や行政の啓蒙活動などに全員が参加し、食生活の改善や進展に貢献すると思われる新しいメニューや調理法の提案を行います。4年生は個人または少人数のグループで現状から抽出された課題の中から卒業研究のテーマを決定し、健康に資する食生活を設計することを目標に、様々な方法で研究に取り組みます。
このゼミを選んだ理由
もともと調理も好きだし、食に興味がありました。さらに食に関わる授業を受けて、自分自身も含めた食生活上の問題を深く掘り下げて考えてみたいと思ったからです。
研究テーマ
「生活習慣が月経痛に及ぼす影響」 女子大学生を対象としてアンケート調査を行い、夜型化や朝食欠食が月経周期異常や月経痛を増悪する可能性を見出し、生活習慣の乱れが月経に悪影響を及ぼすことを明らかにしました。
ゼミの特長
食品開発などゼミのメンバーで協力することが多く、自然と仲良くなります。いつもおいしいものがあって、食器にもこだわった華やかなおやつタイムがゼミ生の楽しみのひとつです。
これまでの主な卒業研究トピック
チョコレートの風味に関する調理学的研究
京野菜の加工特性に関する研究
生活習慣が月経痛に及ぼす影響
若年女性における日本と台湾の食意識の比較



地域福祉と活動-酒井研究室
社会福祉/地域福祉/福祉教育
教員紹介

酒井久美子 さかい くみこ
担当科目
生活と福祉、コミュニティと福祉、コミュニティ活動実践
研究分野
社会福祉、地域福祉、福祉教育
研究のこだわり
社会福祉協議会や高齢者、障がい者等の各種事業所など、さまざまな地域の事業、活動との協働を大切にしています。
2年間のゼミの流れ
3年次には、地域福祉に対する理解を深めること、地域活動に取り組み、多様な地域課題について理解を深めることを大切にしています。 4年次には、それらを踏まえつつ、各自の研究テーマに沿って、卒業研究に取り組みます。
このゼミを選んだ理由
対象者を限定するのではなく、地域という広い範囲で福祉、地域福祉について考えたいと思ったから。
研究テーマ
住民の主体形成にかかわる福祉教育について
ゼミの特長
地域の障がい者就労支援事業所の商品販売(学内パン販売や大学祭、NDクリスマスへの出店など)ゼミ単位での活動が盛んです。学外での活動にも取り組んでいます。活動を通して、経験できること、福祉の現状や課題について学ぶことができます。また、自分たちのしたいことがあれば先生も手助けをしてくれるので、やりたいことや興味のあることを応援してくれるゼミだと思います。



人間関係をめぐる共生と福祉-三好研究室
高齢者福祉/ソーシャルワーク学/対人援助技術学
教員紹介

三好明夫 みよし あきお
担当科目
高齢者と福祉、生活と社会保障
研究のこだわり
「人間関係」をさまざまな角度から考える
現代社会では、様々な場面で人と人との出会いを育み、繋ぎ、よりよい人間関係の構築のために適切な手助けができる専門的な理論、技法、実践を身につけた人が必要となっています。人間関係とは何か、信頼関係とは何かを考えながら行動していくことが必要だと思います。人間、生きていれば必ず老います、そんな「老い」を巡る課題をさまざまな角度から検討していきたいと思いますが、高齢者に言及せず、ゼミのテーマを設定し、全人的に考える「人間関係をめぐる共生と福祉のゼミからのソーシャルワーク学」とさせてもらっています。
2年間のゼミの流れ
人間関係の構築は「人と人との絆づくり」であり、最も大切なことだと思います。ですが、人間関係は簡単には築けないということも感じていると思います。どのようにすれば良い人間関係を築き、豊かな生活が実現できるのか。3年次はフィールドワークやボランティア活動などから卒業研究の方向性を探っていきます。そして4年次には探求した卒論テーマに向かって卒業研究をゆっくり、しかし確かな歩みとして行っていきます。
このゼミを選んだ理由
福祉の現場で働くときに人間関係を豊かにすることは不可欠だから。・どのような仕事をしても人間関係がよくなければ前に進めない。・人が差別したりいじめたりする環境をなくしていきたい、そのためには関係性の在り方を学びたい。・音楽活動での人間関係を良好にする方法を考えたい。・動物介在活動を行うことでの人間関係の改善について考えたい。
研究テーマ
通所リハビリテーションでのレクリエーションの目的と効果について / デイサービスを利用している要介護高齢者の楽しみについて / デイサービスセンターにおけるレクリエーションの効果と課題について / 視覚障害を持つ高齢者のためのコミュニケーションの工夫について / 超高齢社会に必要とされる在宅サービス、デイサービスとデイケアの役割 / 特別養護老人ホームにおける利用者の生きがいにつながる食事について / グループホームにおける食事摂取低下の利用者への食事支援の工夫について / 特別養護老人ホームの利用者が行う「書道活動」における心の効果について / グループホームの利用者に対して化粧を行うことの効果について / ジャニーズJr.平野紫耀耀のヲタクにおける行動の特性について
ゼミの特長
人間関係を繋ぐためにどうしたらよいのか。例えば、そこには動物が介在するかもしれませんし、アイドルが介在するかもしれません。ですが、人は他者との関係性において繋がっています。こんな不思議を「なぜ、どうして」と様々な角度や視点から考えて探していく。


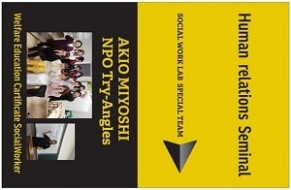
これまでの主な卒業研究トピック
高齢者
デイサービス
老人ホーム
グループホーム
ヲタク
装いの心理学-牛田研究室
被服学/被服社会心理学/アパレルデザイン
教員紹介

牛田 好美 うしだ よしみ
担当科目
衣生活概論、服飾心理学、アパレルデザイン
研究分野
被服学、被服社会心理学、アパレルデザイン
研究のこだわり
被服や化粧など、外見(見た目)にかかわる装いは、自分自身、そしてそれを見る他の人に大きな影響を与えます。装いがもつ人の心を動かす力を研究し、誰もが生き生きと毎日の生活、そして、自分らしい人生を送るための研究をしています。
2年間のゼミの流れ
3年次前期は、ウェデングドレスデザイン、カラー診断、美術館やファッションイベント見学など、体験的な授業で幅広く学びます。3年次後期は、卒業論文のテーマに沿った文献を読み、研究計画をたてます。4年次に入るとすぐに調査を実施し、論文執筆に入ります。
このゼミを選んだ理由
ファッションに興味があるから。美容に興味があるから。化粧が好きだから。
研究テーマ
女子大学生のファッションに関する意識と実態 / 女子大学生の化粧に関する意識。身体意識と被服行動。女子力に関する調査
ゼミの特長
幅広い被服に関する体験をします
これまでの主な卒業研究トピック
香り
和服
ヘアスタイル
双子コーディ
SNSとファッション



食と健康-加藤研究室
食/健康/高齢者
教員紹介

加藤佐千子 かとう さちこ
担当科目
食生活概論、食品官能評価論、食品加工学(実験を含む)
研究分野
高齢者の食と健康
研究のこだわり
高齢者研究というと、支援(介護など)の必要な虚弱な方を想像してしまいがちですが、私は、元気な高齢者を研究対象としています。すなわち、健康を維持し、病気や体力の低下を防ぐには、どのような食物をどのくらい摂取したらよいのかについて研究しています。特に、日頃の食習慣を変容するには、人々の心理に介入する必要があり、食物を摂取・選択する時の心理的な要因にも関心をもって研究をしています。
2年間のゼミの流れ
<3年次>
4 月 研究計画書を作成
4 ~ 5月 論文の検索方法,読み方,書き方を学ぶ
6 ~ 7月 先行研究の発表,考察の仕方を学ぶ
10 ~12月 テーマを絞り,関連論文の収集する
12 ~1月 統計や分析の基礎を学ぶ。テーマの決定
2 ~3月 調査用紙の作成,予備調査,予備実験
<4年次>
4~6月 調査実施,データ入力および分析
9月 ラフコピー提出
9~11月 データ分析、および論文執筆
12月1日 卒論提出
このゼミを選んだ理由
・食について研究したかった ・食と健康について興味があったから ・食分野について興味があったから ・先生との相性よかったと感じたから ・先生に相談した時、自分に合っているかなと感じた ・卒論指導が丁寧な先生だから ・どのような食が健康的になるか知りたかった ・加藤先生の授業を受けていて知っている先生だったから ・卒論の時、先生が教えてくれると思った ・興味のある卒論が書けると思った
研究テーマ
・女子大生の美容整形に対する意識 ・女子大生の食生活・睡眠・運動と月経随伴症状との関連 ・スーパーフードの認知と使用実態 ・K女子大生の外食状況 ・女子大生のブランド品に対する意識と実態
ゼミの特長
本ゼミでは,健康,健康心理,食生活,教育に関連する事柄から,自分の興味のあるテーマを決めて研究をします。子ども,大学生,中年,高齢者など対象として,上記の事柄と関連したテーマを考え研究します。また,家庭科教育と関連のあることをテーマとして研究することもできます。質問紙やインタビューによるデータ収集のほか,官能評価実験により求めたデータをもとに論文を仕上げていきます。 高齢者との交流会を毎月1回しています。


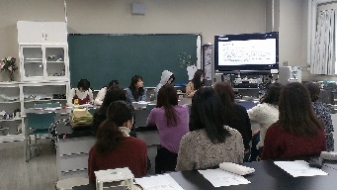
精神保健福祉-佐藤研究室
精神保健福祉
教員紹介

佐藤 純 さとう あつし
担当科目
精神疾患とその治療
研究分野
精神に「障害」のある人の家族支援
研究のこだわり
家族会の相談やグループ活動等の実際の支援を通して、精神に「障害」のある人へ家族の求める支援を研究している。家族支援の対象は、本人と、本人の親、きょうだい、配偶者、子どものすべてが対象で、メリデン版訪問家族支援という本人と家族をまるごと支援する技術を英国より日本に導入し、普及する取り組みにもチャレンジしている。
2年間のゼミの流れ
ゼミはもともと苗床の意味です。精神保健福祉ゼミは、卒業論文を書き上げる重要な場(苗床)ですが、それと同時に感受性豊かな福祉職を育てる場(苗床)として、さまざまなことにも取り組んでいます。その年に集まった学生と相談しながら2年間のゼミの計画を立てて実行に移します。そして最後には自分の満足する卒業論文を書き上げることも目標にしています。
ゼミの特徴
3年生では、さまざまなゼミでの活動を通じて(2022年度は精神に「障害」のある人が通う作業所さんと一緒に学内販売を計画)経験を通じて学ぶことと同時に卒業論文に必要な研究方法を身につけていきます。 4年生では、卒業論文の調査や執筆を進めますが、同時に就活や国試もあわせて進める必要があり、ゼミ生同士で支えあって乗り切れるように、毎週ゼミ生同士が集まって指導していきます。 卒業時には自分なりに満足できる大学生活と進路決定を目標にゼミ活動を進めています。

研究テーマ
精神に「障害」のある人や家族の支援に関するテーマが多いですが、ゼミ生の関心のあるテーマに沿って卒業研究をすすめていきます.
概要
精神障害者の家族支援/精神障害者のリカバリーへ向けた支援など
このゼミを選んだ理由
・ゼミ生それぞれの思いや個性を大事にしてくれる。 ・自分らしくもいれるし、仲間ととりくむ楽しさもある

これまでの主な卒業研究トピック
精神障害 発達障害 家族 ひきこもり きょうだい おたく
住環境-竹原研究室
住環境 / 雰囲気評価 / 人間工学
教員紹介

竹原 広実 たけはら ひろみ
担当科目
住居学概論、住環境デザイン、住環境学
研究分野
住居学、建築環境工学(温度、湿度、光、気流、空気、音などみえない環境要素を計画をする)、建築人間工学、感性工学 (人の感覚、知覚、心理、行動、動作の特性を知り、それを建築や空間計画に生かす)
研究のこだわり
快適な住環境、空間をつくるための設計要因を探る研究をしています。特に人の感覚・心理量(快適性)と物理環境要因との関連を解明することに関心をもっています。
2年間のゼミの流れ
卒業研究に向け、3年次は建築、住居に関する知識や視野を広げることを目的として資格勉強をします。4年次、実験や調査を実施し、卒業論文を仕上げます。研究の過程で論理的に思考し、課題に対して解決策(提案)を導き出す力を身につけてもらうことを期待します。ゼミでは産官学連携活動に積極的に取り組んでいます。(株)ノーリツ、京都上下水道局、(株)電通といっしょに、お風呂好きを増やす活動を展開しています。また学内、学外問わず、建物や空間に関する依頼があればどんなことでも具体的な提案、実施を手掛けます!2022年に大学施設のリフォームを実施しました!
このゼミを選んだ理由
住居に興味があり、資格の勉強もしたかったからです。授業で建築や住宅はとても機能的に考えられていることを知り、もっと知りたくなりました。測定器などを使った実験をして研究をしてみたかったです。
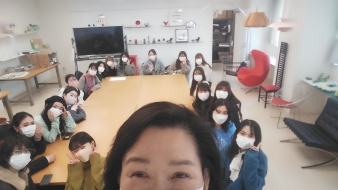
研究テーマ
雰囲気評価実験研究 / 住宅居間の色彩実測調査 / 屋外環境調査と評価実験の研究(JR京都駅ビル大階段と下鴨神社)/ 高齢者の生活行動に関する実験研究 / 台所の動作に関する実験研究 /地域の住環境ニーズに関する研究
概要
雰囲気評価実験は、画像処理技術を用い、同一空間で壁、家具、色彩など条件(変化要因)を変化させた対象空間を作成します。それを被験者に評価させることで、どの変化要因が雰囲気に影響を及ぼしているか検討を行います。 屋外環境調査は、屋外の物理条件(気温、湿度、風速、音、照度、日射量、放射温度)などを測定するとともに、被験者がその地点でどう感じるか(暑い、寒い、じめじめする、など)の評価と照らし合わせ、心地よい環境となるための条件を探ります。

ゼミの特長
インテリアデザインラボの飾り付け、デザイナーズチェアの手入れも勉強の一環として行います。また聴竹居など近代建築の見学やインテリアデザインの実際や流行を学ぶ目的でイケア見学などを行います。

これまでの主な卒業研究トピック
室内雰囲気 色彩 高齢者 身体活動量 地域住環境
ソーシャルマーケティング-新村研究室
準備中 / 準備中 /
教員紹介

新村 佳史 にいむら よしふみ
担当科目
マーケティング論、ライフプランニング論
研究分野
準備中
研究のこだわり
準備中
2年間のゼミの流れ
準備中
このゼミを選んだ理由
準備中
研究テーマ
準備中
概要
準備中
ゼミの特長
準備中
これまでの主な卒業研究トピック
準備中
