研究室紹介
英語英文学科では、文化、文学、言語学、コミュニケーション学、英語教育学について研究しています。本ホームページでは、各研究室での研究の内容やゼミ生の声などを紹介しています。
Global Issues
Global Issuesでは、国際社会が抱える諸問題について様々な角度から考察し、また異文化に対する理解を深めることによって、実践的な国際適応力を養います。
The purpose of this seminar is to introduce students to the major topics in sociolinguistics—the study of the relationship between language and society. We will cover a wide variety of topics in the field of sociolinguistics, which may include: regional and social language variation; language and identity, power, ethnicity, gender, sexuality, and social contexts; language attitudes, language contact, and multilingualism.
2年間のゼミの流れ
In the first year, students will gain an understanding of the field of sociolinguistics and become familiar with sociolinguistic theory and methods. Students will also learn about field methods, data gathering, and analysis. In addition, students will learn how to apply sociolinguistic concepts to critical approaches to language teaching.
Students will submit a proposal for their graduation theses at the beginning of the second semester and begin writing the first chapter. They will complete their theses during the fourth year.
教員紹介

York Weatherford ヨーク ウェザフォード 准教授
担当科目
Listening, Speaking, Advanced Reading, Advanced Writing
研究分野
Teaching English to Speakers of Other Langauges, Extensive Reading, Computer Assisted Language Learning, Bilingualism
最近の研究活動

Presentation
Using Popular Music to Motivate University EFL Students
Presentation at the 17th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching

科学研究費 挑戦的萌芽研究
『新しい多言語学習環境の構築 -英語による中国語学習、中国語による英語学習-』(2015〜2017年)
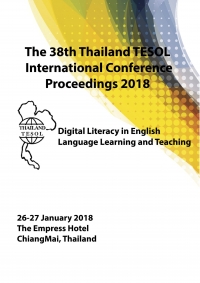
Article
Extensive Reading for Increased Reading Speed and Comprehension
In The 38th Thailand TESOL International Conference Proceedings 2018
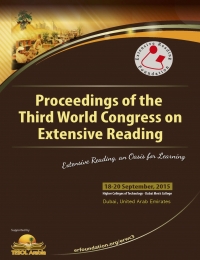
Article
An Evaluation of Progress Measurement Options for ER Programs
in Proceedings of the Third World Congress on Extensive Reading

Article
Student Assessment Preferences in an ER Program
in JALT2014 Conference Proceedings
Culture&Literature
文化・文学研究では、英語圏文化および文学作品の深層に多角的な視点から切り込み、社会の仕組みや思想、文学的主題が孕む普遍的な人間性を論理的に探求します。
ゼミでは学生間で意見を交換し、文学作品の言葉ひとつひとつから発見する新しい世界と、そこから見える作品の景色をたのしんでいます。
最近では、1853年に発表されたメルヴィルの「バートルビー」という短編小説を読んでいます。
当時の時代背景を踏まえつつ、作品の分析から見えてくる主題について考察します。
英語、内容ともに難解ですが、じっくり精読しつつ、ゼミ生と一緒に内容について議論し、「読みの愉しみ」を味わっています。
2年間のゼミの流れ
3回生から始まる「英語英文学演習」(ゼミ)では、アメリカ文学の小説を精読し批評します。
4回生から始まる「卒業研究」、各ゼミ生が文学作品を選び、各自が設定する研究計画にしたがって、卒業論文の執筆を行います。
毎週補講を実施し、各学生からの経過報告をしております。
加えて、個人面談を通じ論文指導を適宜行い、卒論の完成を目指します。
先輩の声 小西 のぞみ (4回生)
このゼミを選んだ理由
私が大川ゼミを選んだ理由は、もともと読書が好きで、大学で文学を学び、より文学を探求したいと思ったからです。二回生の時に「米文学の歴史」という授業で『白鯨』という小説に興味を持ち、それについて学べることも大川ゼミに入るきっかけになりました。

研究テーマ
Sympathy and Antipathy for Physical Deficiency: A Study of Lafcadio Hearn’s Works (身体的欠如への共感と嫌悪—ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)作品研究
概要
ラフカディオ・ハーンのKwaidanにおける幽霊などの身体表象に着目し、ハーンの伝記的背景に絡めて分析を行っています。 最終的に、身体的欠如がハーンにとって何を意味しているのかについて考察したいと思っています。

ゼミの雰囲気
大川ゼミでは、H・メルヴィルの「バートルビー」という作品を原文で読んでいます。
英語表現がわからないところや、気になるところなどについて、先生を含めゼミ生全員で議論しています。
和気あいあいとしているため、様々な意見がでて楽しい雰囲気で活動しています。
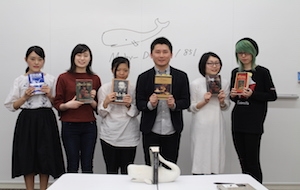
これまでの主な卒業研究トピック
Rethinking Roaring Twenties: Morality and Immorality in The Great Gatsby
Who is “Black”?: Racial Motifs in Auster’s Ghosts.
King Kong in 19th Century: A Study of Poe’s “The Murders in the Rue Morgue”
The Self-Destructive Tragedy: The Narcissistic Imagery in Moby-Dick
Hester and Her Letter: Phantasmagoric Visionary in The Scarlet Letter
教員紹介

大川 淳 おおかわ じゅん
担当科目
学部:米文学の歴史、アメリカの社会と文化、英語英文学演習Ⅰ/Ⅱ
英語英文学基礎演習Ⅰ/Ⅱ、専門講読Ⅰ/Ⅱ、Academic WritingⅠ/Ⅱ、卒業研究
大学院:英文学批評特論、応用英語研究方法論、専門演習
研究分野
19世紀アメリカ文学を主に研究しています。19世紀アメリカ文学を代表するハーマン・メルヴィルとナサニエル・ホーソーンの作品を中心に研究しています。
最近ではアメリカ文学作品を食の表象から、分析し整理することが課題です。
また、アメリカ文化史、特にサブカルチャーなどにも興味があり、そこからアメリカ文化の形成についての研究も行っています。
研究のこだわり
文学作品は言葉によって紡がれていますが、その言葉ひとつひとつを掘り下げていくと、物語の新しい表情を見ることができます。「神は細部に宿る」という言葉がありますが、それを研究のモットーに、時代背景などを踏まえつつ、ひとつひとつの言葉とその関係を分析しながら、文学作品にあたらしい意味を見出することを目指しています。
最近の研究活動

著書(共著)
「皮膚、テクスト、鏡ーー「痣」におけるエールマーの罪のしるし」
(『ロマンスの倫理と語り : いまホーソーンを読む理由』 西谷拓哉, 髙尾直知, 城戸光世 編著, 開文社, 2023, pp.287-304)

著書(共著)
「転覆する「アメリカ」—「ピアザ」における虚構の旅路」
(『アメリカン・ロード―光と陰のネットワーク』花岡秀編著、英宝社, 2013,pp.74-95.)

論文
海岸の想像力ーー『タイピー』における暴力と官能のトポス
(Sky-Hawk: The Journal of the Melville Society of Japan, no 10, 2022, pp. 38-54.)
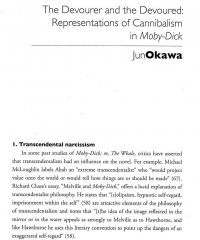
論文
The Devourer and the Devoured: Representations of Cannibalism in Moby-Dick
(Sky-Hawk: The Journal of the Melville Society of Japan, no 6, 2018, pp. 51-65.)
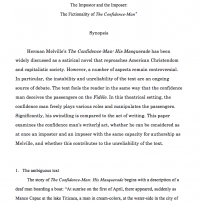
論文
The Impostor and the Imposer: The Fictionality of The Confidence-Man
(『英米文学』第62巻第一号, 関西学院大学英米文学会, 2018, pp.33-55.)
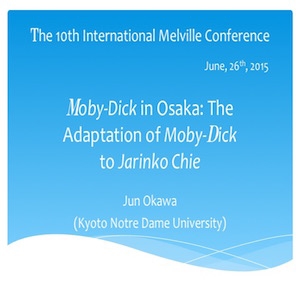
学会発表(国際学会)
“Moby-Dick in Osaka: The Adaptation of Moby-Dick to Jarinko Chie”
(The Tenth International Melville Conference, 2015)

その他(社会貢献活動)
エッセイ「「食べる」こと、「食べられる」こと--食文化と文明」
(Kyoto Experiment・ magazine, 京都国際舞台芸術祭, 2021年)
(https://kyoto-ex.jp/magazine/2021s-article-2/)
このセミナーでは、日系人文学を探究します。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどの国々には、日本人の子孫である300万人以上が暮らしています。ノーベル文学賞受賞作家の石黒一雄氏をはじめ、大学の文学コースで読まれる重要な作家たちがいるのも驚くことではありません。なぜ彼らが重要なのでしょうか?これらの作家たちは、アイデンティティ、ステレオタイプ、人種、移民体験、そしてジェンダーなど、今日の世界で重要な問題について最先端の執筆を行っています。学生たちは卒業する頃には、日本人のアイデンティティについての理解が深まり、英語の読み書き能力が向上し、文章の読み解き技術を通じて文学を論じ分析する能力が身につくでしょう。このセミナーは、英語のフィクションを読むことが好きで、日本人のアイデンティティや日本人の子孫であることの意味を探究したい学生、そして今日起こっている重要な問題について学びたい学生に適しています。
2年間のゼミの流れ
https://www.lyledesouza.com/teaching/de-souza-seminar-nikkei-diaspora-literature
日系作家による英語圏の短編小説を、大学二年次の秋学期に取り上げます。学生たちは文学分析を学び、三年次および四年次に向けて高度な研究の準備をします。三年次の春学期には、イギリスとアメリカの日系文学を学びます。その後、私たちは神戸を訪れて日本からの移民について学びます。これは、日本の移民歴史と日本人コミュニティの形成に関する理解を深めるための実地調査の一環となります。三年次の秋学期には、カナダと学生が選んだ国の日系文学を学びます。そして、最後に、大学四年次の授業では卒業論文の執筆と提出を支援します。
先輩の声 大須賀 凪
このゼミを選んだ理由
私がライルゼミを選んだ理由は外国で暮らす日本にルーツを持つ人たちの生活に興味を持ったからです。また、日系移民文学という初めて触れる分野で日系人の歴史や苦難を文学を通して学ぶことができると思いこのゼミを選びました。

研究テーマ
概要
On the Reality and Conflicts of Post-war Japanese American Life in “No No Boy” (“No No Boy”における戦後の日系アメリカ人の実態と葛藤) 第二次世界大戦後のシアトルを舞台にした作品から日系アメリカ人のアイディアンティティや世代別の苦悩を読み解きました。

ゼミの雰囲気
非常に仲が良く和気あいあいと授業をしています。文学ゼミなので英語で本を読む機会が非常に多いですが、分からないところはみんなで話し合い解決したり、卒業研究での悩みなどもみんなで共有しています。
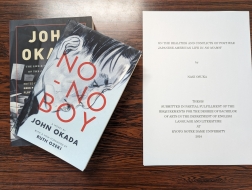
これまでの主な卒業研究トピック
“Klara and the Sun”: The Future of Human and AI Coexistence
Immigration and Social Class in Kazuo Ishiguro’s “Klara and the Sun”
The Life of Stevens in Kazuo Ishiguro’s “The Remains of the Day”
Marxist Hierarchical Society in “Klara and the Sun”
The Importance of Mutual Understanding in “Chorus of Mushrooms”
教員紹介

Lyle De Souza ライル デ スーザ
担当科目
Specialized Reading (American Literature)
Classic Novels of English Literature
Global Japan Studies
Intercultural Communication & Acculturation
Public Speaking
Research Skills
Literary Criticism
Clinical Medicine / Hospital Training
研究分野
Nikkei diaspora literature
race
identity & belonging
literary criticism
研究のこだわり
ライル・デ・スーザ博士は、京都ノートルダム女子大学英語言語文学科の准教授で、人種化のメカニズムを分析してマイノリティのアイデンティティ理解を向上させるための研究を行っています。彼は、文学批評、文化研究、日本研究、社会学の多分野にまたがる学際的な知識を活用し、人文科学と社会科学に掘り下げた研究を行っています。現在の研究プロジェクトである「日系グローバル文学:ディアスポラ、人種、アイデンティティ&帰属」(KAKENHI 21K12957)では、ディアスポラ文学内の人種、アイデンティティ、帰属の交差点を探求しています。
最近の研究活動
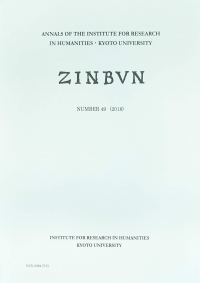
Contesting Canada’s Narrative of Nation through Canadian Nikkei Children’s Literature
This paper argues that modern Canadian Nikkei children’s literature about incarceration contests Canada’s national narrative. Using an interview with a Canadian Nikkei children’s book author and close readings of three works by Canadian Nikkei authors, the paper demonstrates how they challenge the narrative of the nation during the Second World War. The paper highlights how Canadian Nikkei writers can challenge long-held ideas of what makes a nation despite their unequal access to political power and media resources.

Japanese Popular Fiction: Constraint, Violence and Freedom in Kirino Natsuo’s Out
This chapter explores Japanese popular fiction, focusing on Kirino Natsuo’s novel Auto (Out) as an illustration of its significance during times of media and cultural upheaval and major social changes in Japan. The chapter investigates how the novel tackles various social issues such as gender discrimination, an aging society, precarious employment, minority exclusion, and violence. By analyzing the materiality of the novel, the chapter demonstrates how Japanese popular fiction can be used as a tool to observe and address important social issues in Japanese society.
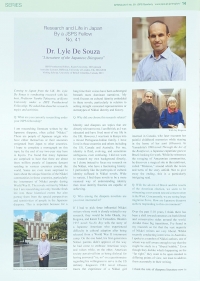
JSPS Research and Life in Japan: Dr. Lyle De Souza
Article by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) about the research and life in Japan of Dr. Lyle De Souza.
https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/english/e-quart/jsps_fellow/jsps_quarterly59.pdf
Language & Communication
言語とコミュニケーション研究では、普段我々が何気なく使っている 「言語」と「コミュニケーション」の仕組み、文化や社会との関係を理論的・科学的に追求します。
1950年代にNoam Chomskyによって提唱された生成統語論は、理論的な発展・変遷とともに細かな修正・改変を経てきました。中でも1990年以降に展開されたミニマリスト・プログラムおよびカートグラフィー理論を基に、文法における「格」というものがどのような働きを持っているかについて研究しています。格は、単に主語、目的語といった文法関係を表すだけでなく、話者の気持ちを表すことがあります。例えば、英語のwhyに似た理由疑問表現であるwhat forでは、前置詞のforが目的格を与えているだけでなく、非難や意外性などの気持ちを表します。また、日本語でも「なぜ」の代わりに「なにを」のような理由疑問表現が使われますが、これにも同じような性質があることが分かっています。これらが使われる文法上、談話上の環境や決まりを解明するのが現在の目標です。
2年間のゼミの流れ
2回生のプレゼミで生成統語論の理論的変遷と基本事項を確認したあと、3回生ではミニマリスト・プログラムとカートグラフィー理論に基づく著書・論文を講読します。それらの先行研究の内容及び自身の卒業研究のテーマについて口頭発表を行い、理解を深めると同時に卒業論文のアウトラインを作成します。4回生の卒業研究では卒業論文個別指導を中心に行います。
教員紹介

田口茂樹 たぐち しげき
担当科目
学部:ことばのしくみ、言語学概論、英語英文学演習 I/II、卒業研究ほか
大学院:日英語比較分析b、応用英語研究方法論、専門演習ほか
研究分野
主に言語学の講座を担当しています。ゼミや研究のテーマは、生成文法理論に基づく統語論です。難しそうに聞こえますが、簡単に言うと文法の科学的な研究です。皆さんは今まで、句や文は線状に並んでいる、単語の羅列にすぎないと考えてきたのではないでしょうか?生成統語論では、句や文が立体的な構造を持っており、それによって文法上の規則や法則が導き出される、という観点から分析を行います。統語論だけでなく、言語学そのものの楽しさを分かち合えるような講義を提供したいと考えています。
Teaching English
英語教育研究では、主に日本の教育現場における英語教育と英語学習に焦点を当て、 効果的な英語教授法および学習方法の在り方について理論と実践の両面から探求します。
何気なく受けている授業ですが、教える側の目的と意図からだけで作られているわけではなく、教える行為と学ぶ活動の相互作用から設計→修正→実施されています。そのため授業は絶えず変化しています。ゼミでは、学ぶという立場から教育や学習場面を分析しながら、どのように、制度、研修、授業が組み立てられているかを説明できる力をつけていただきたいと思います。
先輩の声 蛭子阿子
このゼミを選んだ理由
私は英語社内公用化に関心ありました。最近日本はグローバル化が進んでおり、世界的にも有名な日本企業は社内公用語を英語にしています。そのメリットや変化を詳しく知りたいと思い選びました。
研究テーマ
The Difference Between UNIQLO and Rakutan
概要
会社の公用語を英語としているユニクロと楽天を研究しています。公用語を英語に変更する前と後の2社を分析しながら企業理念、研修制度、特徴を比較しています。
ゼミの雰囲気
ゼミでは、早期英語教育と英語社内公用化についての日本の現状の文章を読みます。難しい内容の時もありますが、分かりやすい説明をしていただけるので安心できます。さらに定期的に様々な仕事をされている方に来ていただいて、お話を聞く機会があります。これはゼミだけではなく就職活動にも役立ちます。
教員紹介

東郷多津 とうごうたづ 教授
最近の研究活動
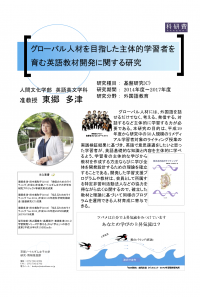
科学研究費 基盤研究(C)
『グローバル人材を目指した主体的学習者を育む英語教材開発に関する研究』(2014〜2017年)
第二言語習得の成否に関わる重要な要因である「動機づけ」に注目して、授業改善について研究します。外国映画や音楽を教材として導入し、英語の背景にある文化を理解することを通して実践される授業が、学習者の学習意欲や英語力向上にどのような影響を及ぼすのかについての調査研究などが挙げられます。さらに、異文化理解に関心を持つ皆さんと一緒に、アメリカ現代文化史に焦点を当てて、映画や小説に込められたメッセージや「時代を動かす人物とその言葉」などについて研究を進めましょう。
教員紹介

喜多容子 きたようこ
担当科目
学部:英語科教育法Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ,こども英語(理論編・実践編), Advanced Reading Ⅰ/Ⅱ
外国語(理論編・実践編)
大学院:応用言語学, 応用英語研究方法論
研究分野
英語科教育,異文化理解教育,そして小学校英語におけるICTの効果的な活用を中心に研究を進めています。最近は,「時代を動かす人物とその言葉」に興味を持ち, 女性の社会的地位向上に多大果たした果たしたRuth Bader Ginsburgについての研究も行っています。
研究のこだわり
私は、英語教育学を専門としていますが, 同時に異文化理解・国際理解教育にも興味を持って、研究に取り組んでいます。映画に込められた人種差別・性差別などの社会的な問題に対するメッセージや「時代を動かす人物とその言葉」について, 新たな考察を加えたいと考えています。
最近の研究活動

学会発表
The Attitudes of Japanese University Students toward Domestic Labor and their Implications for Gender Parity (3rd Global Conference On Women’s Studies, February 2022)

学会発表
Small Talk Activities for College Students Pursuing Elementary School Teaching – Small Talk Project Year 2–(the 19th Annual CamTESOL Conference,18 Feb 2023)
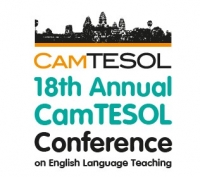
学会発表
“Small Talk in English Lessons” A New Challenge to Elementary School Educators in Japan (the 18th Annual CamTESOL Conference,20 Feb 2022)

学会発表
A Comparison of Women’s Social Progress Between the U.S. and Japan -Breaking the glass ceiling in RBG style- (JALT Kyoto Annual General Meeting, Nov 2021)

論文

論文
Working Women in Japan and the Complications of Hiring Household Help (Journal and Proceedings of the Gender Awareness in Language Education, Vol.13, 2021:49-65)
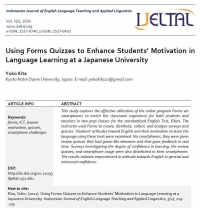
論文
Using Forms Quizzes to Enhance Students’ Motivation in Language Learning at a Japanese University (Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics, 5(2), 2021 : 219-235)
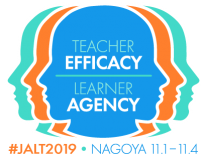
学会発表
Effective Collaboration in English Education(JALT 2019: 45th Annual International Conference on Language Teaching and Learning & Educational Materials Exhibition, November, 2019)

学会発表
Effective usage of ICT in review and feedback in EFL class (JALT CALL 2020 Online Conference, June 2020)

Article
Breaking the glass ceiling to join a man’s world in Ruth Bader Ginsburg’s “A life” ― The comparison of the social progress of women between America and Japan-(Naruto Society of English Studies, Vol.28, 2020 : 211-218)

論文
The Critical Period Hypothesis and English Language Education: EFL at primary and middle schools in Japan (Research Bulletin of Naruto University of Education,Vol.33, 2018 : 309-316)

学会発表
Fostering university students’ teaching skills through learner-centered instruction
(The 8th Japan-China Teacher Education Conference, November, 2019)
Career Program
英語英文学科では、社会奉仕のための英語修得を目的とする、キャリアプログラムを開講しています。 各領域の専門家による指導のもと、それぞれのキャリアに接続する実践的な英語とスキルを学びます。
外国人が日本で安心して医療を受けられるように、英語力と医療の専門知識を備えた人材を養成します。
京都府立医科大学附属病院で実習を予定しています。医療現場はもちろん、医療・製薬系企業、観光・旅行業界んどでの活躍が期待されます。
主な就職先
- 大学院進学(通訳系、医療系)
- 病院受付
- 航空業界
- ホテル業界
2020年度にCOVID-19感染拡大の影響で留学が中止/延期になったことを受け、英語英文学科では、これを補うプログラムとして、また、今後も海外留学の代替として選択できるプログラムとして、本学独自の Campus Study Programをスタートさせました。
時差や費用の問題の多い海外の語学学校のオンライン科目の受講ではなく、本学英語英文学科がコーディネートする独自の企画により、日本国内および海外で活躍する英語母国語教員を招聘したプログラムに参加します。学生のみなさんは、春季・夏季休暇中、あるいは学期中の適切な時間帯に、本学キャンパスあるいは自宅から自由に参加できます。
準備中です
